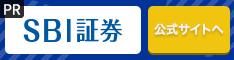こんにちは、ゆうすけです。
Follow @learntoushi
皆さんは日本株に投資していますか?
私のポートフォリオの50%超は米国株を中心とした外国株(投資信託含む)ですが、
日本株にも10%程度は投資しています。
日本株投資に利用しているのが「単元未満株」と言われる1株単位で買えるサービスです。
色んな証券会社がこの「単元未満株」サービスを出している中で私が使っているのはSBI証券です。
少し前まではSBIネオモバイル証券を使っていましたが最近移行しました。
そこで今回は、単元未満株のメリット・デメリットとSBI証券をおすすめする理由を紹介します!
- 少額から日本株投資を始めたい
- ネットで気軽に投資を始めたい
- まずは低リスクで株式投資をしたい
単元未満株ってなに?
まずは「単元未満株」について説明しましょう!
単元というのは、株式の売買単位のことです。
日本株を売買しようとすると株価が1000円なのに100,000円無いと買えない
といった銘柄を見たとはないでしょうか?
これは株式の売買単位=単元が100株からになっているんですね。
日本では1単元=100株と規定されている銘柄が多いです。
一方で米国は1単元=1株から買える銘柄が多いので、米国株から始める人が増えた理由にもなってますね。
ただ、100株からしか買えないために日本株を買うハードルが高くなっている現状があります。
例えばファーストリテイリング(ユニクロ運営会社)の株価は2022年4月28日時点で約60,000円です。
ユニクロ大好きな人が

と思ったら600万円が手元に必要ということです。
さすがにフツウの人では買えないですよね…
そこに出てくるのが単元未満株です。
単元未満株は定められた単元より少ない株数で購入ができる株式のことです。
売買単位は100株が多い日本株を、1株から買えるということですね。
単元未満株のおかげで少額から投資を始めたい投資初心者の強い味方です。
私も日本株の多くはこの単元未満株で買っています。
- 単元=株式の売買単位
- 1単元=100株
- 単元未満株=単元未満の数で買える株
単元未満株のメリット・デメリット


気軽に少額から買えるという大きなメリットがある単元未満株にはデメリットもあります。
しっかりメリットとデメリットを知った上で利用するようにしてくださいね。
単元未満株のメリット
- 少額から買える
- 複数銘柄に分散投資しやすい
- 配当をもらえる
少額から買える
単元未満株は1株から買えるので銘柄によっては100円単位から株を買うことができます。
100株単位だと株価が300円でも最低30,000円が必要ですが、300円なら気軽に投資を始められますよね。
少額で買えるということは、リスクを抑えられるので投資初心者や投資元本が少ない人にとって大きなメリットなります。
複数銘柄に分散投資しやすい
少額から買えるので、同じ投資元本でも単元で買うよりも複数の銘柄に分散投資がしやすくなります。
「一つのカゴに卵を盛るな」
という投資の格言があるように、一つの銘柄に資金を集中投資するのはリスクが高くなります。
なるべく複数の違う会社の株を買うことでリスクを分散させるのは投資の鉄則でもありますね。
単元=100株だと1つの銘柄にかける資金が多くなるので、資金に限りのある人は自ずと「一つのカゴに盛りがち」になります。
それが単元未満株なら同じ資金額でも1株から買えるので複数の銘柄を買うことができますね。
極端な例を示すと、
10,000円もっていたら
株価100円の1銘柄を100株買うよりも、
株価100円の100銘柄を1株ずつ買うほうがリスク分散になります。
こうして単元未満株は分散投資の強い味方になってくれます。
配当をもらえる
単元未満株でも単元売買と同じように株式数に応じた配当金をもらえます。

といったレベルに行くまでは道のりが長いですが、
それでも株からの配当金をもらうという経験は超うれしいです。
単元未満株でもコツコツと買い続けていけば配当金も増えていきます。
株式投資を始めるハードルを下げられて、
少額でも配当金を貰う経験を得て
株式投資の成功体験を積むことができる
これが単元未満株で日本株への投資を始めるメリットそのものですね。

単元未満株のデメリット
単元未満株のメリットを紹介してきましたが当然いいことばかりではありません。
デメリットも紹介するのでぜひメリットと比較してご自身の判断に役立ててください。
- 株主優待が付かない
- 成行購入しかできない
- 議決権がない
株主優待が付かない
多くの雑誌やネット記事で株式投資の魅力の一つに「株主優待」が挙げられますが
単元未満株の多くは株主優待を貰う権利がありません。
中には1株からでも優待をくれる企業もありますが極まれですね。
株主優待の条件には「1単元以上を保有していること」というのが入っていることが多いので単元未満株では貰えません。
私は投資において株主優待はあくまで「オマケ」だと思っているのでデメリットには感じていませんが、豪華な食品詰め合わせやカタログギフトを目的に投資を始める人がいるのも事実です。
なので株主優待目的の人は単元未満株ではなく単元から売買をするようにしましょう。
成行購入しかできない
単元未満株は購入時に成行でしか買えません。
つまり指値購入が出来ないということです。
成行というのは、買値をこちらから指定せずに市場価格で購入(売却)する、という売買方法です。
一方で指値というのは、○○円になったら買う(売る)、という条件をつける売買方法です。
成行だと自分が買いたい売りたいと思った価格とは違う価格で成約してしまうことがあります。
更に単元未満株は購入手続きから成約までタイムラグが長い(半日~一営業日後)ので
「買おう!」と思った価格では買えないことが多いので要注意ですね。
このタイムラグは証券会社によって異なるのでよく調べるようにしましょう。
議決権がない
この記事を読んでくれている方でこれを欲しがる人はあまりいないと思いますが笑、
保有株数が単元未満だと株主総会での議決権が基本的にはありません。
株主総会で各議案の多数決に参加するには一定の株式数を保有していることを条件にしている企業がほとんどなので100株未満の株主は対象外にされてしまいます。
私も議決権が欲しかったらさすがに単元で買うのでこれをデメリットに感じたことはありませんが、
知らずに単元未満株で買ってあとから「議決権行使したかった!」となるとガッカリすると思うので紹介しました。

単元未満株を買える証券会社
ここまで単元未満株について紹介してきたので、ようやく単元未満株を買える証券会社を紹介します!
私はネット証券しか使わないので、ここで紹介するのはネット証券かつ私が使っている(使ったことがある)サービスになってます。
- SBI証券
- マネックス証券
- SBIネオモバイル証券
- LINE証券
それぞれの比較はこちらです。
| 証券会社 | 手数料 | 取扱銘柄数 | 特徴 |
| SBI証券 | 0.55% (売却時) |
東証 全銘柄 |
買付手数料は全額キャッシュバック |
| マネックス証券 | 0.55% (売却時) |
東証名証 全銘柄 |
買付手数料無料 |
| SBIネオモバイル証券 | 月220円 (50万円まで) |
東証 全銘柄 |
ポイント付与で手数料実質18円/月 |
| LINE証券 | 0.2%~0.5% (夜間は1.0%) |
東証の約1500銘柄 | たまに3~7%OFFのセール |
手数料はSBI証券とマネックス証券がほぼ同じで、ネオモバが月額制という変わった手数料体系になっています。
LINE証券はスマホ特化型のサービスで取扱銘柄数は少なめですがたまにセールをやっていて市場価格より安く株を買うチャンスがあります。
この中でも私がイチバンおすすめなのはSBI証券です。
かつてはSBIネオモバイル証券を使ってました(今も保有はしています)が、
SBI証券の手数料がキャッシュバックのおかげで安くなったので乗り換えました。
ここでようやく本日のメインである
SBI証券の単元未満株「S株」をおすすめする理由について紹介します!
SBI証券のS株をおすすめする理由3選
単元未満株を買うならSBI証券を勧める理由は次の3つです。
- スマホアプリから買える
- NISA口座で買える
- メインの証券会社で買える
スマホアプリから買える
SBI証券はスマホアプリ「SBI証券 株アプリ」からでも単元未満株(以降、S株)を買うことができます。
これは手数料も取扱銘柄数もほとんど同じなマネックス証券との大きな違いですね。
マネックス証券は機能も銘柄も充実していて手数料も下げてきましたがスマホアプリに対応していません。
どちらかといえば玄人向けであるマネックス証券は単元未満株を買うような初心者にはハードルが高いでしょう。
NISA口座で買える
NISAとは、通常は20.315%かかる運用益への税金を非課税にできる国の制度で、一人一口座まで持つことができます。
NISA口座は年間120万円まで投資が出来て、個別株や投資信託、REITなどを購入できます。
このNISA口座でS株を買えるのはSBI証券とマネックス証券です。
スマホ証券と言われるネオモバやLINE証券ではNISA口座は利用できません。
運用益が非課税になるのは投資利益面ではとても大きいので使わない手は無いでしょう。
ちなみに最近有名な「つみたてNISA」ではS株は買えません。
S株が買えるのは通常の「NISA」なので注意が必要です。
メインの証券会社で買える
SBI証券はS株だけでなく、通常の単元株から米国株、NISAやジュニアNISA、iDecoやロボアドまで広く投資サービスを提供している大手ネット証券です。
そのためメインの証券会社として利用している人も多いのではないでしょうか。
私もその一人です。
最近は投資方法が多様化している代わりに口座やウェブサイトの管理が煩雑になりがちです。
(IDパスワードをいくつも持ったり、運用成績をそれぞれのアプリで確認したり)
ここに単元未満株を買う証券会社をさらに新しく加えるのはメンドクサイ…
そう思っていた私にとってはSBI証券で買えるのは大きなメリットでした。
投資初心者の方々のなかには「まだそんなに沢山サービス使ってないよ」という人もいると思いますが、
あなたが初心者でなくなる(沢山サービスを使うようになる)日はそう遠くありません!
なので今のうちから纏められるものは「メイン証券会社にまとめる」ようにしましょう!

まとめ
いかがでしたでしょうか!?
本日は単元未満株を買うならSBI証券のS株をおすすめする理由について紹介しました。
- 単元=株式の売買単位
- 1単元=100株
- 単元未満株=単元未満の数で買える株
- 少額から買える
- 複数銘柄に分散投資しやすい
- 配当をもらえる
- 株主優待が付かない
- 成行購入しかできない
- 議決権がない
- SBI証券
- マネックス証券
- SBIネオモバイル証券
- LINE証券
- スマホアプリから買える
- NISA口座で買える
- メインの証券会社で買える
まだSBI証券の口座を持っていない方は無料で口座開設できるのでこちらのページから申込みをどうぞ。
今回の記事が良かった!という方はぜひTwitterフォローと「読者になる」ボタンのクリックをお願いします!
ゆうすけ
※関連記事です
SBI証券について紹介しています
SBI証券で米国株を始めるならこちら
マネックス証券も紹介しています
SBIネオモバイル証券も使いやすいですよ
米国株を手軽に始めるならPayPay証券がおすすめです